一般内科について
 泌尿器科疾患はお付き合いを続けていく病気が多くその診療の中で生活習慣病と呼ばれている高血圧、脂質異常症(高脂血症)、糖尿病、痛風(高尿酸血症)をはじめとした慢性疾患が見つかる事があります。
泌尿器科疾患はお付き合いを続けていく病気が多くその診療の中で生活習慣病と呼ばれている高血圧、脂質異常症(高脂血症)、糖尿病、痛風(高尿酸血症)をはじめとした慢性疾患が見つかる事があります。
些細な症状での受診が病気の早期発見につながり、深刻な症状にさせずに治せるケースもあります。「気になる症状や不調がある」「どの診療科を受診すべきかわからない」「漠然とした健康不安がある」などの場合にも気軽にご相談ください。
また、かかりつけの方で急な発熱や感冒症状といったいわゆる急性期内科疾患も可能な限りで対応いたします。お気軽にご相談ください。
生活習慣病について
生活習慣病とは

食事の偏り、運動不足、睡眠など生活サイクルの乱れ、飲酒・喫煙、ストレスなどの生活習慣が重なって発症・進行する疾患の総称であり、代表的な疾患には高血圧・脂質異常症(高脂血症)・糖尿病があります。
生活習慣病は、動脈硬化を進行させ、狭心症・心筋梗塞などの心疾患、脳梗塞・脳出血・くも膜下出血などの脳血管障害など命に関わる深刻な疾患を引き起こすことから、発症予防や進行防止のための治療が重要になってきます。
メタボリックシンドロームは、内臓脂肪型肥満があり、高血圧・脂質異常症(高脂血症)・糖尿病の複数がある状態です。高血圧・脂質異常症(高脂血症)・糖尿病の検査結果が軽度でも動脈硬化の進行が早く、自覚症状がないまま突然、心筋梗塞や脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)を起こすリスクが高いことから、メタボリックシンドロームと指摘された場合には、できるだけ早く適切な治療を受ける必要があります。
生活習慣病は進行するまで自覚症状が現れにくく、中でも脂質異常症(高脂血症)は進行しても自覚症状は全くありません。生活習慣病を放置し、心筋梗塞や脳卒中を起こしてしまうと、命が助かった場合でもQOL(クオリティー・オブ・ライフ)が大幅に低下し、介助や介護を受けずに生活できる寿命が短くなってしまいます。できるだけ早期に生活習慣病を発見して適切な治療を開始し、良好な状態をしっかり維持するようにしましょう。
なお、生活習慣病は腎臓を含む泌尿器系の臓器にも大きな負担をかけることから、排尿障害(頻尿・夜間頻尿・尿漏れ・尿意切迫感など)、性機能障害(勃起障害など)で受診し、生活習慣病の早期発見につながることも珍しくありません。こうした症状や不調がありましたら、早めの受診をお勧めしています。
生活習慣病は、軽度であればストレスの少ない生活習慣の改善で効果を見込めます。また薬物療法を併用することで健康で快適な生活を維持する事を目指します。気になることがありましたらご相談ください。
当院の生活習慣病の治療
当院では、できるだけストレスなく続けられる内容の生活習慣改善をご提案し、患者様と相談しながら治療方針を立て、親身に寄り添った診療を心がけています。
なお、進行状態により他診療科の専門的な医療が必要と判断された場合には専門医と連携した治療を行っています。また、検査や手術などで入院が必要な場合には、連携している高度医療機関をご紹介し、患者様が適切な医療と迅速につながるようにしています。
高血圧症
診察室血圧では収縮期血圧140mmHg以上、または拡張期血圧90mmHg以上(140/90mmHg以上)が、家庭血圧では135mmHg以上または85mmHg以上(135/85mmHg以上)が続くことで高血圧と診断されます。
血圧が高いと全身の血管に大きな負担がかかって動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)を起こすリスクを上昇させます。また、高血圧は腎機能低下の重大なリスク要因であり、夜間頻尿と高血圧の関連も指摘されています。
高血圧に対する生活習慣改善では、減塩で高い効果を得やすい傾向があります。また、適正体重の維持は高血圧以外の生活習慣病予防・進行防止にも不可欠であり、肥満解消のための食事療法・運動療法が重要になります。こうした生活習慣の改善をしっかり行った上で、必要な場合には薬物療法を併用します。
糖尿病
細胞がエネルギー源として利用するブドウ糖の取り込みを助けるインスリンの分泌や働きが低下し、血液中のブドウ糖が異常に増えた状態が続く病気です。
完治に導く治療法はありませんが、適切な血糖値をキープする治療を続けることで糖尿病の進行や合併症発症リスクを抑制し、良好な状態を維持することが可能になります。食事療法では食事内容だけでなく、食事のタイミングなど食生活全体の見直しを行います。運動療法は、習慣的な軽い有酸素運動で血行や代謝を改善し、筋力をアップさせてインスリンの効果を得やすくします。さらに必要があれば薬物療法を併用し、正常範囲の血糖値を維持できるようにします。
脂質異常症(高脂血症)
血液中の脂質が過剰な状態になる疾患です。過剰な脂質が血管壁にたまって動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)を起こすリスクが高くなります。トリグリセライド(中性脂肪)や LDLコレステロール(悪玉)が過剰、または血中の余分な脂質を回収するHDLコレステロール(善玉)が少ない状態が脂質異常症と呼ばれます。
進行しても自覚症状が現れないことから、健康診断などで脂質異常を指摘された場合には速やかに受診することが重要です。食生活の改善と適度な運動、適正体重の維持、禁煙、節酒などが基本になります。必要があれば薬物療法を併用し、正常範囲を維持していきます。
痛風(高尿酸血症)

血液中の尿酸値が高い高尿酸血症の場合、過剰な尿酸が鋭い針状の結晶となって関節にたまり、激しい痛みを起こす痛風発作を起こすことがあります。尿酸値が高いまま続くと、尿路結石や腎臓病の発症リスクが高くなります。
高尿酸血症と指摘された場合、痛風発作を起こしたことがなくても適切な治療を受けて正常な尿酸値を維持することが重要です。なお、痛風発作を起こした場合には、痛みを緩和させる治療で状態を落ち着かせてから高尿酸血症の治療をスタートさせます。急激な尿酸値の変動、ハードな運動、水分摂取不足などは痛風発作を起こす要因になりますので、慎重にコントロールする必要があります。なお、尿酸結晶が関節にたまっている場合には、尿酸値が治療で正常値まで下がってからも結晶が溶けるまで治療を続けることが重要です。
肥満
標準的な体型に見えても筋肉が少なく、脂肪が多い隠れ肥満というケースもありますので、体脂肪率もしっかりチェックする必要があります。
肥満は生活習慣病発症や進行の高リスク要因であり、内臓脂肪型肥満の場合には特に進行リスクが高くなります。心臓病や脳血管障害などの発症リスクを下げるためにも、肥満に当てはまる方は、適正体重を維持することが重要です。
腎臓内科
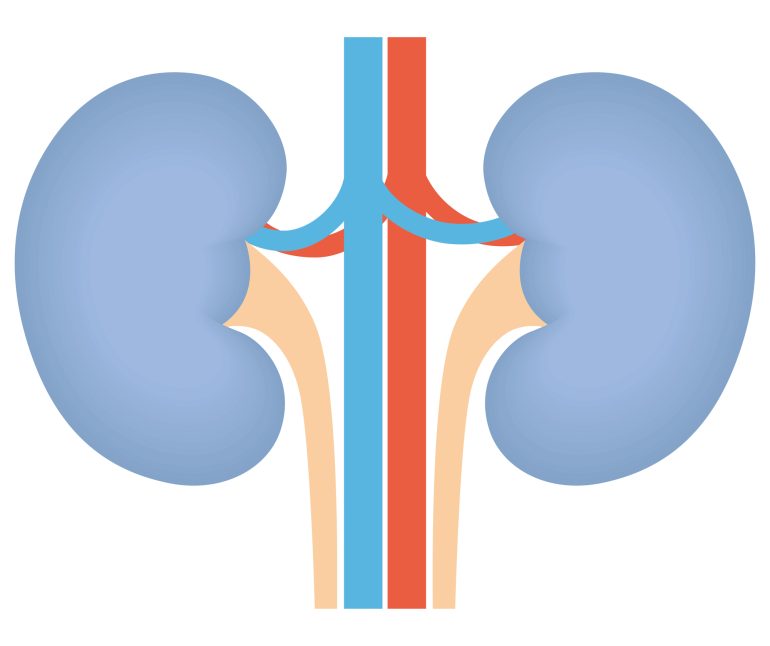 健康診断で行われている尿検査は様々な疾患の発見に役立ちます。特に腎臓や尿路などの疾患が発見されることが多く、尿検査異常を指摘された際には腎臓内科・泌尿器科の受診が有効です。尿検査異常を指摘されたら、早めにご相談ください。
健康診断で行われている尿検査は様々な疾患の発見に役立ちます。特に腎臓や尿路などの疾患が発見されることが多く、尿検査異常を指摘された際には腎臓内科・泌尿器科の受診が有効です。尿検査異常を指摘されたら、早めにご相談ください。
健康診断で指摘される
「尿検査の異常」
健康診断の尿検査では、タンパク尿、尿潜血、尿糖などを調べます。尿潜血は肉眼では確認できない微量の血液が尿に混じっていないかを確認します。見た目で血液が混じっているとはっきりわかる場合には、肉眼的血尿と呼ばれ、ご自分で気付くこともあります。
血尿
 血尿は、血液をろ過して尿を作る腎臓、尿が通る尿路(尿管・膀胱・尿道)のどこかで出血が起こっているサインであり、主に腎臓や尿路の疾患によって生じます。そして、血尿に痛みが伴わない場合は泌尿器のがんが疑われます。肉眼的血尿・尿潜血を含む血尿は泌尿器がんの早期に現れることもある症状ですので、速やかに受診することで完治に導く治療につながる可能性があります。血尿に気付いたらできるだけ早くご相談ください。
血尿は、血液をろ過して尿を作る腎臓、尿が通る尿路(尿管・膀胱・尿道)のどこかで出血が起こっているサインであり、主に腎臓や尿路の疾患によって生じます。そして、血尿に痛みが伴わない場合は泌尿器のがんが疑われます。肉眼的血尿・尿潜血を含む血尿は泌尿器がんの早期に現れることもある症状ですので、速やかに受診することで完治に導く治療につながる可能性があります。血尿に気付いたらできるだけ早くご相談ください。
尿潜血
見た目ではわからないほど微量の血液が尿に含まれており、尿を顕微鏡で観察してはじめて発見できることから顕微鏡的血尿とも呼ばれます。泌尿器がん、尿路結石、膀胱炎、糸球体腎炎などが疑われますので、早めの受診をお勧めします。
タンパク尿
腎臓病、そしてそれ以外の疾患によって生じた腎機能障害が疑われ、できるだけ早く原因疾患を特定し、適切な治療を受ける必要があります。腎臓病では、急性腎炎・慢性腎炎、それ以外の疾患では糖尿病・高血圧・膠原病などが疑われ、必要な治療が異なりますので、正確な診断をできるだけ早く受けることが重要になります。
透析療法
腎臓の機能が低下してしまった際に腎代替療法として血液透析、腹膜透析、腎移植があります。
当院ではそれらに関する治療は原則行っておりません。必要な方は近隣施設に紹介させて頂きます。
健康診断で尿の異常を指摘された場合、血液検査、超音波(エコー)検査、そして尿沈渣(尿中沈殿物分析)などの精密な尿検査などが行われます。その上でさらに必要があれば膀胱鏡検査などを行って診断します。
腎臓と高血圧
高血圧は、遺伝的素因に生活習慣の乱れが関与して発症する本態性高血圧が知られていますが、他の病気が原因となって高血圧を生じる二次性高血圧もあります。二次性高血圧は、副腎疾患や腎動脈狭窄などの腎臓疾患を原因として生じやすいとされており、生活習慣改善や降圧剤などの薬物療法の効果を得にくく、原因疾患の適切な治療によって高血圧の改善が期待できます。高血圧全体の10%程度が二次性高血圧と指摘されており、決して少なくない比率ですので、原因疾患の有無を調べることはとても重要です。
インフルエンザ
インフルエンザの予防
インフルエンザは、例年冬期に流行する感染症で、急に高熱が出て、その後に関節痛や筋肉痛、咳などの症状が現れるという特徴を持っています。高齢者や基礎疾患により免疫力が低い場合、重症化しやすく、肺炎や脳症など深刻な合併症を起こすこともあります。発症や重症化の予防には、流行シーズン前の予防接種が有効です。予防接種の効果は、接種から2週間程度で現れはじめ、約5ヶ月間続きます。11月末までに予防接種を受けておくと、流行シーズンをカバーできます。
なお、13歳未満では2回接種が推奨されており、2~4週間の間を開ける必要があります。2回接種の場合、十分な効果は2回目接種の2週間後から得られるとされていますので、1回目接種を10月中に受けるようお勧めしています。
早めの受診で適切な治療を
 インフルエンザは一般的な風邪よりも強い症状が出て、感染力も強く、重症化により命の危険につながる合併症を生じる可能性のある感染症です。特に免疫力が低い高齢者、糖尿病・心臓病・腎臓病などがある方、呼吸器疾患のある方は重症化・合併症のリスクが高く、注意が必要です。抗原検査は症状が出現してもすぐには陽性になりません。一般的には発症後12時間から48時間以内の検査を推奨されております。そのため熱が出てからすぐに検査をしても陰性とでてしまうため適切な治療が受けられません。しかし早期に診断できれば重症化予防につながる有効な治療が可能になりますので、疑わしい症状が12時間超えて続く場合には早めに受診しましょう。
インフルエンザは一般的な風邪よりも強い症状が出て、感染力も強く、重症化により命の危険につながる合併症を生じる可能性のある感染症です。特に免疫力が低い高齢者、糖尿病・心臓病・腎臓病などがある方、呼吸器疾患のある方は重症化・合併症のリスクが高く、注意が必要です。抗原検査は症状が出現してもすぐには陽性になりません。一般的には発症後12時間から48時間以内の検査を推奨されております。そのため熱が出てからすぐに検査をしても陰性とでてしまうため適切な治療が受けられません。しかし早期に診断できれば重症化予防につながる有効な治療が可能になりますので、疑わしい症状が12時間超えて続く場合には早めに受診しましょう。
費用
| 予防接種 | X,XXX円(税込) |
|---|
健康診断
※ 現在準備中です。










