排尿時痛について
(しみて熱っぽい・じわじわ痛い)
排尿時痛とは
 おしっこをする際に、しみるような熱っぽい痛みが生じている状態で、痛む部位は尿道や下腹部です。排尿の最初に痛みがある、最後に痛みがあるといったタイミングの違いで原因疾患がある程度判断できます。緊急性が低いと思い放置してしまったことで腎盂腎炎や敗血症に移行してしまい重篤になってしまう可能性があります。
おしっこをする際に、しみるような熱っぽい痛みが生じている状態で、痛む部位は尿道や下腹部です。排尿の最初に痛みがある、最後に痛みがあるといったタイミングの違いで原因疾患がある程度判断できます。緊急性が低いと思い放置してしまったことで腎盂腎炎や敗血症に移行してしまい重篤になってしまう可能性があります。
また、性感染症の場合は、大事な方に移してしまう危険性もあります。排尿時痛があらわれた方はできるだけ早くご相談ください。
排尿時痛の原因
尿道が痛い場合
尿道に細菌感染による炎症が起こっている可能性が高く、他に尿路結石や膀胱炎が疑われます。痛みが起こるタイミングが排尿の最初の場合は尿道の感染が疑われ、最後の場合にはそれ以外の原因疾患が疑われます。
下腹部が痛い場合
膀胱や尿道の炎症によって生じている可能性が高く、尿路結石も疑われます。また、腎盂腎炎や敗血症など、できるだけ早く適切な治療が必要な危険な疾患の可能性もあり、原因を確かめることが重要です。なお、膀胱炎は女性に多い疾患であり、適切な治療で治りやすい疾患ですが再発を繰り返しやすく、慢性化させてしまうことも珍しくありません。慢性化すると腎盂腎炎を繰り返すことで腎臓機能障害に発展する可能性があります。泌尿器科を受診して再発予防を視野に入れた治療を受け、しっかり治すことが重要です。
排尿時痛を起こす主な疾患
急性膀胱炎
排尿の最後にツンとしみるような強い痛みを起こしやすい疾患です。頻尿、尿の濁りや血尿などの症状を伴うこともあります。尿道から入り込んだ細菌が膀胱粘膜に感染して炎症を起こしており、男性に比べ尿道が短い女性の発症が多く、免疫力が低下していると感染しやすくなります。
冷えやトイレの我慢など生活習慣も発症の要因で、再発を繰り返しやすい傾向があります。慢性化や再発を繰り返すと難治性になり、腎機能障害を進行させてしまう可能性がありますので、適切な治療を受け、再発させないことが重要です。
前立腺炎
男性だけにある前立腺は、膀胱の下、尿道を取り囲むように存在していますので、前立腺が炎症を起こすと隣接した尿道や膀胱を刺激して様々な症状を起こします。初期の前立腺炎では、排尿の最初に排尿時痛が起き、頻尿や残尿感などを伴うこともあります。炎症が悪化すると痛みが強くなり、高熱を伴い排尿障害が生じる事があります。深刻な排尿障害や腎臓へのダメージを生じさせないためにも、疑わしい症状がありましたら早めにご相談ください。
尿路結石症
腎臓でできた結石が尿と共に尿路に運ばれ、膀胱や尿道粘膜を傷つけることで排尿時痛を起こすことがあります。他にも、尿の勢いが弱くなる、頻尿、尿の濁り、血尿、残尿感などを伴うこともあります。なお、狭い尿管に結石が詰まると突然片側の腰部や背部に激しい痛みを起こし、吐き気や嘔吐を伴うこともあります。
腎盂腎炎
腎臓が細菌感染を起こして炎症が生じている状態です。腎機能が大きく損なわれる危険性がありますので、できるだけ早く適切な治療を受ける必要があります。
慢性化した膀胱炎などが背景にあって生じることが多く、排尿時痛が起こるタイミングは、最初から最後まで生じるケースもあるなど様々です。他にも、尿の白濁や血尿、吐き気や嘔吐、高熱、背中や腰の痛みなどが伴うこともあります。腎機能を守るためにも、速やかにご相談ください。
尿道炎
女性に比べ尿道が長い男性に生じやすい炎症です。クラミジアや淋菌などによる性感染症が多くを占めますが、大腸菌などの常在菌によって生じた炎症でも尿道炎を起こすことがあります。また、近年マイコプラズマ・ウレアプラズマによる尿道炎も注目されております。性感染症の場合にはパートナーの検査や治療も不可欠ですので、原因をしっかり確かめることが重要になります。なお、尿道炎は悪化すると尿道の狭窄が進行して尿を出せなくなる尿閉を起こすこともあります。
淋病・淋菌性尿道炎
淋菌による性感染症で、男性が感染すると尿の出はじめに強い痛みを生じ、膿を伴うこともあります。女性は感染してもはっきりした自覚症状がないことが多く、気付かずにいると将来の不妊や早産・流産、母子感染などのリスクが高くなってしまいます。感染がわかったらパートナーにも医療機関を受診するよう伝えることが重要です。なお、淋病はオーラルセックスでも感染しますので、注意が必要です。
性器クラミジア感染症
クラミジアによる性感染症で、男女ともに感染しても自覚症状に乏しく、自覚症状がある場合も軽い排尿時痛や尿の白濁程度です。気付かないまま感染が拡大しやすい傾向があり、若い女性の感染が増加していることが指摘されています。将来の不妊につながる可能性がありますので、できるだけ早く発見して適切な治療を受け、しっかり治すことが重要です。オーラルセックスでも感染することがあります。感染がわかったら必ずパートナーにも検査を受けるよう伝えてください。
排尿時痛を予防するためには?
排尿時痛が現れたら、速やかに泌尿器科を受診することが重要です。ただし、女性の場合、子宮頚部などの検査が必要な場合があり、婦人科への受診をお勧めすることがあります。なお、性感染症は、男女で現れる症状の内容や程度が大きく異なります。ご自分だけ症状がありパートナーには症状がなくても感染している可能性が高く、繰り返し感染しないためにもパートナーの検査が不可欠です。
免疫力を下げないために
休息や睡眠をしっかりとって、栄養バランスのとれた食事を3食規則正しくとりましょう。適正体重を維持するためにダイエットを行う場合も医師に相談して栄養の偏りが起こらないよう注意する必要があります。また、身体を冷やすと感染を起こしやすくなりますので、冬は足腰を冷やさないよう注意し、夏もできれば毎日バスタブに浸かって身体を芯まで温めましょう。
なお、糖尿病をはじめとした免疫力が低下する疾患がある場合や免疫抑制剤を用いた治療を受けている場合には、治療をきちんと受けて状態を安定させ、良好な状態を維持することを心がけてください。
性交渉時にはコンドームを
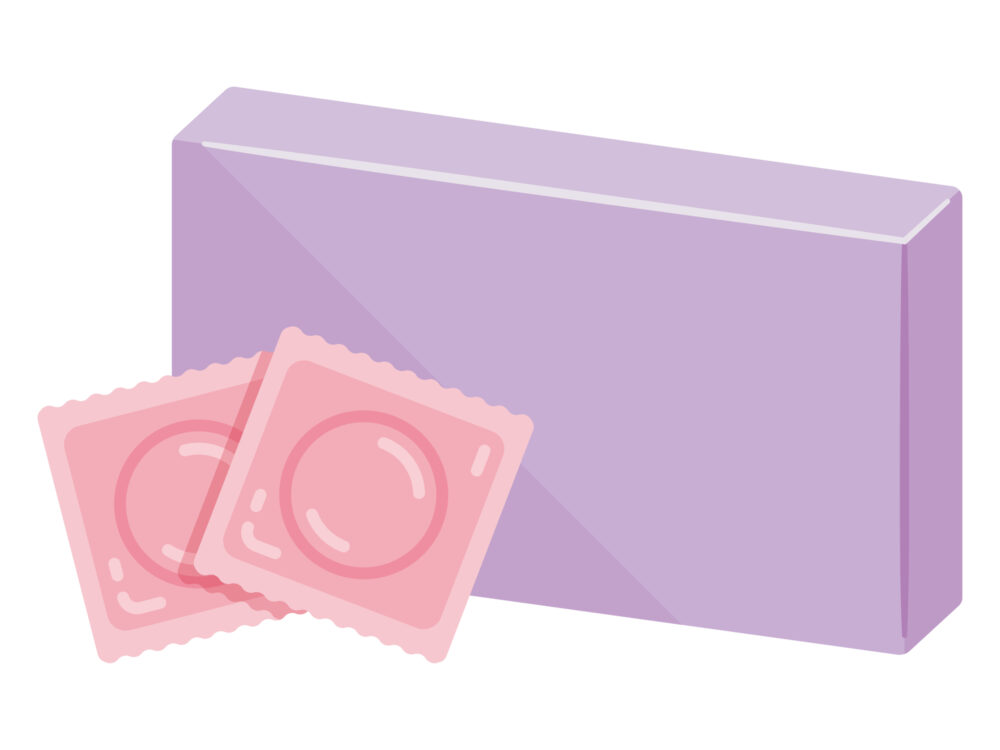 性交渉の際に正しくコンドームを装着することは、性感染症予防に有効です。正しく装着しても途中からの場合は感染リスクが高くなってしまいますので注意してください。ただし、最初から最後まで正しく装着していても感染リスクはゼロにはなりません。また、オーラルセックスで感染する場合もあります。尿道炎・膀胱炎を予防する手立てとして性交渉後にそのままにせず、排尿するという手段があります。疑わしい症状や心当たりがありましたら、お気軽にご相談ください。
性交渉の際に正しくコンドームを装着することは、性感染症予防に有効です。正しく装着しても途中からの場合は感染リスクが高くなってしまいますので注意してください。ただし、最初から最後まで正しく装着していても感染リスクはゼロにはなりません。また、オーラルセックスで感染する場合もあります。尿道炎・膀胱炎を予防する手立てとして性交渉後にそのままにせず、排尿するという手段があります。疑わしい症状や心当たりがありましたら、お気軽にご相談ください。
尿の濁り
尿の濁りとは
 健康な方の尿は透明で黄色かがっています。水分摂取量や汗などの多さにより色が少しだけ変化しても問題がない場合が多いのですが、透明感がなく濁りがある場合には泌尿器疾患が背景にある可能性が高くなります。尿中に含まれるリン酸・シュウ酸などの結晶化した塩類によって白濁している場合は、尿路結石の疑いがあります。また、尿路感染症や血尿によって尿が濁っている可能性もあります。
健康な方の尿は透明で黄色かがっています。水分摂取量や汗などの多さにより色が少しだけ変化しても問題がない場合が多いのですが、透明感がなく濁りがある場合には泌尿器疾患が背景にある可能性が高くなります。尿中に含まれるリン酸・シュウ酸などの結晶化した塩類によって白濁している場合は、尿路結石の疑いがあります。また、尿路感染症や血尿によって尿が濁っている可能性もあります。
尿が濁る原因
食生活による尿の濁り
 特定の食品を過剰に摂取すると、リン酸やシュウ酸などの塩類が結晶化し、尿が濁りやすくなります。特に、ホウレンソウやバナナ、ゴボウ、ココア、さらには動物性脂肪を多く含む肉類を摂りすぎると、尿中のシュウ酸カルシウムの結晶が増え、白濁の原因となることがあります。
特定の食品を過剰に摂取すると、リン酸やシュウ酸などの塩類が結晶化し、尿が濁りやすくなります。特に、ホウレンソウやバナナ、ゴボウ、ココア、さらには動物性脂肪を多く含む肉類を摂りすぎると、尿中のシュウ酸カルシウムの結晶が増え、白濁の原因となることがあります。
女性に起こる尿の濁り
女性はおりものや経血が尿に混じって白濁しているように見えるケースがあります。他の症状(陰部のかゆみ・不快感、排尿時痛、頻尿など)を伴わない場合には、しばらく様子をみて、白濁が一過性であればそれほど心配する必要はありません。ただし、他の症状を伴う場合や、白濁が続く場合には疾患が背景にある疑いがあります。
特に女性に多い膀胱炎が慢性化した場合、無症状で炎症が続いているケースがありますので、早めの受診が必要です。
性病(性感染症)による尿の濁り
尿の濁りは性感染症で起こりやすい症状です。最近では、20代の淋菌・クラミジア感染が拡大しており、10代の感染も増加傾向にあることが指摘されています。自覚症状に乏しいことで感染が拡大しやすく、誰もが感染する可能性のある疾患となっています。淋菌やクラミジアによる感染症は珍しくない病気ですが、放置していると女性の不妊症・男性の不妊症を起こす可能性があり、早産や流産、母子感染などのリスクもあります。男女で症状の内容や強さが異なるケースがあり、片方に症状がなくてもお互いに感染している可能性が高いので、感染がわかったらパートナーにも必ず検査を受けるようお伝えください。
血尿による尿の濁り
膀胱炎や尿路結石によって、尿管・膀胱・尿道などの粘膜が傷付き、出血すると血尿を起こします。出血量が少ない場合、尿の色に赤みがなく、濁りを生じることがあります。尿検査をすることで見た目ではわからない微量出血の有無も確認できます。血尿は泌尿器がんなどでも生じる症状であり、早期発見につながることもあります。尿の濁りに気付いたら、できるだけ早くご相談ください。
尿の濁りを起こす主な疾患
尿の濁りは、腎臓や膀胱、尿管、尿道といった尿路、男性の前立腺など、様々な泌尿器の疾患によって起こる症状です。炎症や結石、感染症などが多くを占めますが、泌尿器のがんによって生じることもあります。なお、感染症で膿が生じた場合、強く白濁することがあります。
腎結石・尿管結石
腎臓内でシュウ酸・リン酸、尿酸などが結晶化し、腎盂や尿管を通る際に粘膜を傷付けて出血することで、尿の濁りが生じます。出血が多ければ肉眼ではっきりわかる血尿となりますが、微量の出血の場合には尿の濁りとして感じられます。頻尿、残尿感、尿の勢いが弱いなどを伴うこともあります。
また、尿管は長く、途中に細くくびれた部分があり、そこに結石が詰まってしまうと腰や脇腹、背中などに突然、激しい痛みを起こします。あらゆる疾患の中でも強い痛みを起こし、吐き気・嘔吐などを伴うこともあります。
腎盂腎炎
腎臓に細菌が入り込んで感染し強い炎症を伴う病気です。尿中の白血球が多くなって白濁し、吐き気・嘔吐、排尿時痛、血尿、高熱、背中や腰の痛みなどを伴います。慢性化した膀胱炎があると免疫力が低下した際に腎臓まで感染が広がりやすくなります。腎盂腎炎を繰り返したり、放置したりすることで腎機能低下を起こすリスクが高く、できるだけ早く適切な治療を受ける必要があります。膀胱炎の再発を繰り返す場合は、泌尿器科を受診してしっかり治し、再発を防ぐことが重要です。
急性膀胱炎
尿道から入り込んだ大腸菌などが膀胱粘膜に感染して炎症を起こしている状態です。尿の濁り、頻尿、排尿の最後に起こるツンとした特有の排尿時痛、血尿などを起こします。尿道が短い女性の発症が多くを占めており、冷えやトイレの我慢といった生活習慣も発症に関与することから再発を繰り返しやすい傾向があります。泌尿器科を受診してしっかり根治させ、再発を防ぐことが重要です。
尿道炎
淋菌やクラミジアの感染によって急性炎症が引き起こされるケースが多くあります。放置すると尿道が狭くなり、排尿困難に陥る危険性もあります。特に男性に多くみられる炎症ですが、自覚症状が乏しいため、知らぬ間にパートナーへ感染を広げてしまう可能性があります。心当たりのある方は、ご自身だけでなく、パートナーも検査・治療を受けることが重要です。
淋菌感染症
淋菌に感染して尿道に炎症を起こします。男性が感染すると尿の出はじめに強い排尿時痛を起こすことが多いのですが、膿が混入して尿が濁ることで気付くケースもあります。女性は感染しても無症状のことが多く、症状があっても軽いかゆみやおりもの程度です。ただし、感染を放置していると不妊の原因になる可能性があり、母子感染によって赤ちゃんが失明するケースもあります。パートナーに症状がなくても必ず婦人科を受診するようお伝えください。
性器クラミジア感染症
クラミジアによって発症する感染症です。女性の性感染症では最も患者数が多く、若い女性にも広がっていることが指摘されています。男性は感染によって尿の出はじめに軽い排尿痛を起こし、炎症が進行して化膿すると尿に濁りを生じます。女性は感染しても自覚症状に乏しいのですが、放置していると不妊や母子感染を起こす可能性があります。誰もがかかる可能性のある感染症であり、特に症状がなくても疑わしい状況の場合には、検査を受けて感染の有無を確かめることが大切です。
前立腺炎
前立腺は男性だけにある臓器で、精液の一部である前立腺液を分泌しています。膀胱の下、尿道を取り囲むように存在しており、炎症を起こすと尿の出はじめの強い痛み、頻尿、残尿感などの症状を起こします。炎症が進行すると高熱や尿の白濁を伴うことがあり、痛みが強くなってその範囲も下腹部全体に拡大します。重症化すると前立腺がむくむことで尿が出せなくなることもあることから早めに適切な治療を受け、しっかり治すことが重要です。
腎結核
結核菌が血液に運ばれて腎臓に感染して発症します。初期症状に尿の濁りがあり、進行して腎臓に膿がたまると尿の白濁が強くなります。悪化して腎機能障害が進行すると高熱や下腹部痛を伴うことがあり、腎不全を発症するリスクが高くなります。腎臓は左右に1つずつありますが、最初は片方だけ感染した場合も、もう片方や尿路などに感染が拡大してしまう可能性があります。できるだけ早く発見し、適切な治療につなげるために、尿の濁りに気付いたらできるだけ早くご相談ください。
前立腺がん、膀胱がん、腎臓がん
泌尿器のがんは自覚症状が乏しいまま進行しますが、比較的早く血尿の症状を起こすケースがあります。また、わずかな血液が尿に混じって生じる尿の濁りをきっかけに発見できることもあります。尿の濁りに気付いたら、1回だけの場合も早めにご相談ください。
泌尿器がんが進行するにつれて目で見てわかる血尿を起こすようになり、特に痛みなどを伴わない血尿や強い尿の濁りがある場合にはがんの可能性が高くなります。さらに進行すると尿を出せなくなる尿閉、男性の場合は勃起不全などを起こすこともあります。
なお、前立腺がんの場合、血液を採取して行う前立腺特異抗原(PSA)検査は、スクリーニング検査としても精度が高いので、早期発見に役立ち、健康診断や人間ドックなどにオプションとして組み込めるケースも増えています。
残尿感
残尿感とは
 排尿後に、尿が出きっておらず膀胱に残っているように感じる症状です。実際に膀胱に尿が残っているケースと、残っていないのに感じるケースがあり、疑われる疾患が異なります。実際に残っている場合には神経因性膀胱や前立腺肥大症などが疑われます。尿が残っていないにもかかわらず残尿感がある症状は、急性膀胱炎、過活動膀胱、膀胱結石、膀胱腫瘍など多くの泌尿器疾患に生じます。
排尿後に、尿が出きっておらず膀胱に残っているように感じる症状です。実際に膀胱に尿が残っているケースと、残っていないのに感じるケースがあり、疑われる疾患が異なります。実際に残っている場合には神経因性膀胱や前立腺肥大症などが疑われます。尿が残っていないにもかかわらず残尿感がある症状は、急性膀胱炎、過活動膀胱、膀胱結石、膀胱腫瘍など多くの泌尿器疾患に生じます。
なお、残尿感を起こすことが多い急性膀胱炎は尿検査で感染の有無を確認でき、適切な治療で治すことができます。他の疾患でも残尿感は早期発見につながりやすく、他に症状がない場合は特に心身への負担が少ない治療で治せる可能性が高くなります。気のせい、単なる不調と思わず、残尿感がある方はお気軽にご相談ください。
残尿感の症状を起こす主な疾患
- 膀胱炎(感染による尿路の炎症)
- 前立腺肥大症
- 神経因性膀胱(脳など神経の問題によって生じる疾患)
- 骨盤臓器脱(骨盤底筋群のゆるみによる臓器の脱出)
- 過活動膀胱
- 心因性頻尿
- 膀胱憩室
残尿感の治療
膀胱炎
急性膀胱炎は主に細菌感染によって生じますので、抗生物質による治療で効果が見込めます。最近は一般的な抗生物質が効かない耐性菌が増えており、その場合には感染した細菌の菌種や抗菌薬への感受性を調べる尿培養検査を受けて効果的な治療につなげる必要があります。また、原因菌に関わらず再発しやすい傾向がありますので、泌尿器科を受診してしっかり治すことが重要です。
神経因性膀胱
排尿は脳から送られてきた指令が神経を通じて膀胱に届くことで正常に行われています。神経因性膀胱は、疾患や外傷などによって指令がうまく伝わらなくなり、尿をためる・排尿するなどの機能を正常に果たせなくなっている状態です。原因となった疾患や外傷の治療が不可欠ですが、神経因性膀胱で生じた残尿感の症状は泌尿器科の治療によって改善が期待できます。なお、原因疾患や外傷の治療では改善できない場合、排尿機能障害などによって膀胱炎や尿路感染症、腎機能障害などの発症・進行リスクが高くなりますので、カテーテルによる自己導尿が必要になるケースもあります。当院では、自己導入の指導・管理もしっかり行っていますので、ご相談ください。
骨盤臓器脱
腹部臓器を支えている骨盤底筋群がゆるみ、骨盤内臓器を支えられなくなって脱出に至る疾患です。軽度であれば骨盤底筋群を鍛える骨盤底筋体操を習慣的に行うことで改善できる場合もあります。骨盤底筋体操は骨盤臓器脱をはじめとした疾患の予防にも効果が見込めます。なお、骨盤臓器脱が悪化した場合には手術が必要になりますので、疑わしい場合には早めにご相談ください。
過活動膀胱・心因性頻尿
残尿感に頻尿、尿意切迫感などを伴う過活動膀胱や心因性頻尿の場合には、適切な薬物療法で効果が期待できます。また、水分摂取のタイミングや量をはじめとした生活習慣の見直し、骨盤底筋群などのトレーニングは、過活動膀胱や心因性頻尿の根本的な原因の解決に有効です。










