泌尿器分野のがんについて
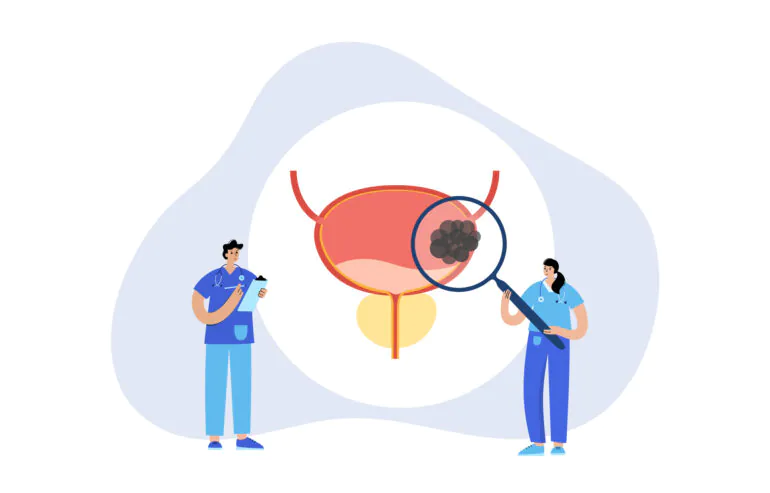 泌尿器科では、腎臓と副腎、尿管・膀胱・尿道、そして男性だけが持つ精巣や前立腺に生じる症状や疾患を専門的に診療しています。泌尿器がんでは、前立腺がんが最も多く、次いで膀胱がん、腎がんの発症が多くなっています。
泌尿器科では、腎臓と副腎、尿管・膀胱・尿道、そして男性だけが持つ精巣や前立腺に生じる症状や疾患を専門的に診療しています。泌尿器がんでは、前立腺がんが最も多く、次いで膀胱がん、腎がんの発症が多くなっています。
一般的にがんは初期症状に乏しい傾向がありますが、泌尿器がんでは血尿をきっかけに早期発見されるケースが少なくありません。血尿は、見た目でわかる肉眼的血尿と、尿検査でわかる顕微鏡的血尿がありますが、どちらの場合でも腎臓・尿管・膀胱・尿道など尿が作られて排出されるまでの間に出血を起こしているサインです。血尿は様々な泌尿器疾患に共通した症状ですが、痛みを伴わずに血尿を生じている場合、比較的がんの可能性が高くなるとされています。
膀胱がんの85%は肉眼的血尿によって発見されており、腎臓がんでも検診以外では肉眼的血尿によって発見されるケースが多いと指摘されています。肉眼的血尿が1度でもあった場合や、尿検査で尿潜血を指摘された場合は、特に他の症状がなくてもできるだけ早くご相談ください。
泌尿器がんのフォローアップ
 がん治療では、早期発見、適切な治療、治療後の経過観察がとても重要です。
がん治療では、早期発見、適切な治療、治療後の経過観察がとても重要です。
当院では、患者様のお話をしっかり伺った上で丁寧に診察し、必要な検査を行って診断した上で最適な治療につなげています。
泌尿器がんが発見された場合も、今後必要になる検査や治療についてわかりやすく説明し、質問にお答えした上で、最適な治療を受けられる連携医療機関をご紹介しています。
また、手術など治療後には、連携したフォローアップを当院で受けて頂けます。コミュニケーションを重視し、患者様に寄り添ったフォローアップに努めていますので、安心してご相談ください。
前立腺がん
最新のがん統計では日本人男性のがん罹患数第1位となっており、中高年男性にとって前立腺がんは最も注意が必要ながんです。発症原因は明らかになっていませんが、加齢、遺伝などの関与があると考えられています。他にも、男性ホルモン、食事、喫煙などの関与も指摘されています。
早期には自覚症状がほとんどありませんが、比較的早い段階で頻尿など排尿障害の症状を起こすことがあります。進行すると様々な排尿障害や血尿などの症状が現れます。ただし、進行し、転移してはじめて腰痛などの自覚症状を起こすケースもありますので、注意が必要です。
自覚症状が現れにくい場合にも早期発見につながるよう、当院では50歳以上の男性にPSA検査(前立腺がんの腫瘍マーカー検査)をお勧めしています。欧米ではPSA検査の受診率が70~80%と高く、前立腺がんによる死亡率も低下傾向にあるとされています。50歳以上、家族歴がある、喫煙習慣があるなど、前立腺がんのリスクを考慮し、検査を検討されている場合には、お気軽にご相談ください。
検査
前立腺がんの可能性を確かめるためのスクリーニング検査を実施し、陽性の場合は精密検査・病理検査によって確定診断を行います。
スクリーニング検査は、PSA検査・直腸内触診・前立腺超音波(エコー)検査の1次スクリーニング検査と、MRI検査による2次スクリーニング検査に分けられます。
PSA検査
 少量の血液を採取して行います。前立腺特異抗原であるPSAという特殊なタンパク質の数値を確かめます。簡便で非常に良い検査ですが、前立腺がんではなくても数値が高くなることがあります。この検査を受ける3-4日以内に激しい運動(特に自転車)や発熱を伴う炎症、射精を伴うような性的な興奮があると数値が高く出てしまいます。検査を受ける際にはそれらを避けるようにしましょう。
少量の血液を採取して行います。前立腺特異抗原であるPSAという特殊なタンパク質の数値を確かめます。簡便で非常に良い検査ですが、前立腺がんではなくても数値が高くなることがあります。この検査を受ける3-4日以内に激しい運動(特に自転車)や発熱を伴う炎症、射精を伴うような性的な興奮があると数値が高く出てしまいます。検査を受ける際にはそれらを避けるようにしましょう。
直腸診
前立腺は直腸に隣接していますので、肛門から指を入れて直腸から触診し、堅さや大きさなど状態を確かめることができます。
前立腺超音波(エコー)検査
お腹の上から超音波を当て、前立腺の大きさ、形状をリアルタイムに観察できる検査です。(見えにくい場合は肛門からエコーを入れより詳細に確認することがあります。きちんとお話しした上で検査は行いますのでご安心ください。)
MRI検査
前立腺がんの有無を精密に調べることが可能な検査です。必要な場合には、連携医療機関をご紹介しています。
前立腺がん検診
(PSA定期検査)
 スクリーニング検査で陽性の場合には、針生検による病理検査で確定診断となります。ただし、針生検は見落としの可能性があり、間隔を開けて複数回行うことで発見されることもあります。こうしたことから、スクリーニング検査陽性で針生検を受け、がんが発見できなかった場合でも継続的にPSA検査を受け、経過を慎重に観察することが重要となります。
スクリーニング検査で陽性の場合には、針生検による病理検査で確定診断となります。ただし、針生検は見落としの可能性があり、間隔を開けて複数回行うことで発見されることもあります。こうしたことから、スクリーニング検査陽性で針生検を受け、がんが発見できなかった場合でも継続的にPSA検査を受け、経過を慎重に観察することが重要となります。
治療
前立腺がんの治療は、経過観察、手術、放射線療法、ホルモン治療、化学療法など選択肢が多く、進行状態、がんの性質、転移の有無、身体状態、年齢など様々な要因を考慮した上で治療法を選択することが重要になります。他の癌種と比べて進行がゆっくりなことが多く、お付き合いを続けていく必要がある癌になります。治療経過が落ち着き当院でのフォローを希望される際には是非ご相談ください。
膀胱がん
膀胱がんは、膀胱内の尿路上皮に発生する表在性膀胱がんが全体の90%を占めており、膀胱壁のどこまで深くがん細胞が及んでいるかによって、筋層非浸潤癌と筋層浸潤癌に分類されます。
女性よりも男性の方が3倍発症しやすいとされており、50~70代の発症が多くなっています。喫煙習慣があると発症リスクは約2~4倍になると指摘されていますので、50~70代の男性で、喫煙習慣がある方は注意が必要です。
主な症状には血尿があり、痛みを伴わない血尿がある場合は尿路上皮癌の可能性が高くなります。血尿は1回だけ生じて、しばらくの間は起こらないこともあります。進行すると現れる他の症状には、頻尿、排尿時の痛み、残尿感、尿意切迫感などがあり、多くの泌尿器疾患と共通した症状を起こします。こうした症状がありましたら、早めにご相談ください。
検査と術後のフォロー
尿検査で微量の血尿がないかを確認します。当院では自動分析装置を用いた、精密な尿検査が可能です。また、採取した尿の尿細胞検査を併せて行い、がん細胞の有無を確認します。さらに、超音波(エコー)検査で膀胱の異常の有無を確認し、病変の大きさや形状、発生部位を確かめ、水腎症の有無なども確認します。
内視鏡による膀胱鏡検査では、尿道からスコープを挿入して膀胱内を直接観察でき、病変のサイズや部位、状態などを詳細に確認できます。なお、膀胱鏡検査では、医療用の麻酔ゼリーを使い痛みや不快感を最小限に抑えています。
膀胱がんは再発リスクが高いとされており、治療後も尿細胞検査や膀胱鏡検査を定期的に受ける経過観察がとても重要になっています。当院では、患者様にきめ細かくフォローアップを行っており、専門医がわかりやすく丁寧に説明し、患者様の質問にも真摯にお答えしていますので、些細なことでも安心してご相談ください。
腎盂尿管がん
膀胱がん同様、腎盂や尿管といった尿路上皮にできるがんのことです。膀胱がんよりも上流にあるため上部尿路上皮癌とも呼ばれます。膀胱鏡などで診断がつけにくいためCTやMRIなどの画像検査を行うことで診断に近づけていきます。
腎臓がん
腎臓は、肋骨の下あたり、背骨の両脇左右に1つずつあります。腎臓に生じるがんは、腎臓の細胞ががん化して生じるがんと腎盂がんがあります。先ほど出てきたように腎盂は上部尿路であり膀胱がんと同様の尿路上皮がんであることから腎臓がんとは呼ばれません。腎臓がん・腎がんと呼ばれるのは腎細胞がんであり、そのほとんどは尿を生成する役割を担う腎実質の細胞ががん化して生じています。
発症は50~70代に多いものの、近年になって30歳以下の発症が増加傾向にあると指摘されています。また、女性より男性の発症が2~3倍高く、喫煙や肥満、長年に渡る透析治療などが腎臓がんの高リスク要因とされています。
初期にはほとんど自覚症状がなく、がんが大きくなると血尿、背中・腰・腹部の痛み、腹部のしこり、足のむくみなどを起こす場合があります。ただし、転移した先で症状を起こすまで発見できないケースもあります。こうしたことから、最近では腎臓の超音波(エコー)検査を行うなど早期発見に向けた検査を組み込んだ健康診断や人間ドックをきっかけに発見されることも増えてきています。
なお、腎臓がんの診断に最も有効であるとされているのは、造影CT検査です。
治療とフォロー
腎臓がんが発見された場合、今後必要となる検査や治療についてわかりやすくご説明し、患者様が納得できる治療を行える連携医療機関をご紹介しています。
以前はがんのある腎臓を全摘出する腎摘出手術が必要でしたが、現在は経過観察や部分的に切除する腎部分切除術が可能なケースが増えてきています。また、開腹手術ではなく、低侵襲で回復も早い腹腔鏡による手術やロボットを使った腎部分切除術が行われることが多くなってきています。また、局所療法では、心身への負担が少ない経皮的凍結療法などが有効なケースもあります。患者様の状態や年齢、将来的なリスクなどを考慮した治療法の相談から、連携高度医療機関による治療後のフォローアップまで、患者様に寄り添った診療を行っていますので、心配ごとや疑問がありましたらどんなことでも遠慮なくご質問ください。
精巣がん
精巣は男性だけにある生殖器であり、陰嚢内の左右に1つずつあります。精巣がんは、発症頻度が10万人に1~2人と非常に低い稀少がんであり、乳幼児や20~40代での発症が多いという特徴を持っています。
精巣がんの家族歴がある、停留精巣の既往があるなどが高リスク要因とされており、痛みがない精巣の腫れやしこりがある場合は精巣がんが疑われます。下腹部の違和感や痛みなどを起こすこともありますが、目立った自覚症状を起こさずに進行し、リンパ節や肺などに転移するまで発見できない場合も少なくありません。
治療とフォロー
触診や超音波検査などで精巣がんが疑われる場合、当院で連携している高度医療機関をご紹介し、できるだけ早く患者様が適切な検査と治療を受けられるようにしています。なお、精巣がんは、発見の時点ですでに微小転移が認められるケースが25~35%を占めていることから、手術に加え、再発予防を目的とした抗がん剤による化学療法や放射線療法などを組み合わせた治療を行う場合もあります。










